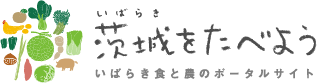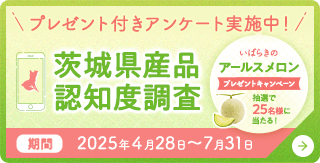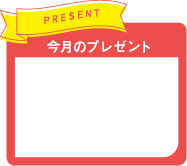PICK UP/ 茨城のうまいもの情報
旬のうまいもの特集
常陸秋そば

~玄そば最高峰と呼び声高きブランドそば~常陸秋そば
全国のそば職人から最高峰の評価を得ているブランド品種「常陸秋そば(ひたちあきそば)」の産地、茨城県。
県北地域は、昼夜の気温差が大きいことや水はけのよい傾斜地など、そばの栽培に適した条件が揃っており、江戸時代から「そばどころ」として知られた名産地です。
県北地域は、昼夜の気温差が大きいことや水はけのよい傾斜地など、そばの栽培に適した条件が揃っており、江戸時代から「そばどころ」として知られた名産地です。
常陸秋そばとは

-
茨城県認定のブランド品種
「常陸秋そば」は、在来種を茨城県が昭和60年に奨励品種として認定したブランド品種です。実が大きく、粒ぞろいが良く、黒褐色の見た目にも大変美しいそばで、香り、味わいに優れています。今や"玄そば(げんそば)の最高峰"といわれる品質を誇り、国内産のそばの中でも高値で取引されています。
「常陸秋そば」の魅力は、なんといってもその粉の力強さ。風味豊かで、通を唸らせる逸品です。東京都内でも、数々の名店で使用されています。口に含んだ時の甘みと、鼻腔に広がる芳醇な香りが特に優れており、その味を求めて多くのファンが県外から足を運ぶほどです。
【そばの豆知識】
そもそも、「玄そば」って?

-
玄そばとは、結実し収穫されたままの殻つきのそばの実のことを指します。黒い殻(外皮)をかぶったままのそばの実のことで、「玄」とは「黒色」という意味です。
そばは穀物のソバの実を原料とするそば粉を原料に作っています。

ソバの実の構造

常陸秋そば誕生物語

-
「常陸秋そば」を「常陸秋そば」たらしめる香りの高さと豊かな滋味は、厳しい選抜育成と種子の管理によって磨きあげられたものです。
古くから茨城のそばは質の高さで知られていましたが、その実態は県内各地の在来種を寄せ集めたものにすぎず、品質のばらつきが大きいものでした。
そこで、茨城ならではのブランドを作り上げようと、1978年に茨城県農業試験場(現:茨城県農業総合センター農業研究所)が新品種の育成に乗り出しました。
金砂郷(かなさごう)の赤土(あかづち)地区(現:常陸太田市)の在来種を親として、選抜育成法により3年余りの歳月をかけて「常陸秋そば」が誕生。粒ぞろいのよさはもちろんのこと、香りの高さと甘みに優れているのが「常陸秋そば」の特長です。そば職人や全国のそば通からも高い支持を得ており、県内で栽培されるほぼ全てを「常陸秋そば」が占めるまでになりました。
一方、そばは他花受粉植物のため品種の交雑が起こりやすく、放っておけばせっかく作った品種であってもその良い性質が失われてしまいます。そこで、「常陸秋そば」の優れた性質を守るのに必要な種子の厳密な管理が現在も続いています。



生産者の声

-
いつでも新そばのようなそばをお届け!
菱沼 英昌さん(桜川市)
丸抜きした常陸秋そばを特殊なアルミ包装で真空にし低温冷蔵庫で保管するという技術を取り入れ、いつ出しても新そばと変わらないほどの色、香り、風味、舌触りを実現しています。
茨城県内だけでなく、全国から注文があり、"そばの名店"と謳われているそば屋さんとの取り引きも少なくありません。
▼いばらきの食に挑戦する人たち
https://www.ibaraki-shokusai.net/seisan/?id=1422
里山に伝承されるご馳走
つけけんちんそば

-
県北地域に伝わるそばは、もともと冬場に食べる主食でした。そばといってもザルに盛った、あるいは出汁にいれたような食べ方ではありません。「つけけんちん」と呼ばれ、具だくさんの汁に太めのそばをつけて食べるものです。
秋の農産物、ネギ、大根、ごぼう、こんにゃく、にんじん、しめじ、芋がらなどが使われます。野菜類を油と味噌で炒め、かつおと昆布の出汁で煮て、醤油とみりんで味付けをします。歯ごたえよく、香りよく、そしておなかの底からからだ全体が温まります。体に優しく、とてもおいしい里山のご馳走は、今でも茨城県北地域の郷土料理として、みんなの生活の中に息づいています。
つけけんちんそばが食べられる店

-
登喜和家(ときわや)
登喜和家の看板商品「けんちんそば」は、具の多さが人気の秘訣。けんちんには欠かせない“芋がら”などおよそ8種類の大きな具がゴロゴロと入ります。
夏は夏野菜をたっぷり使った「夏けんちん」も味わえるため、登喜和家では1年を通して「けんちんそば」を味わうことができます。
茨城県常陸太田市高柿町343
TEL:0294-76-2330
URL:https://www.ibaraki-shokusai.net/shop/shops?id=15441

-
手打ちそば処 金砂そば
金砂そばは、常陸秋そばを“外・二(そば粉10・割粉2)”で味わえるそば店です。
金砂そばの「つけけんちん」は、こだわりのつゆに、野菜から出る出汁が加わって、打ち立ての外二そばとの相性が抜群です。
※つけけんちんの提供期間:10月~5月初旬(冬けんちん)、7月~9月(夏けんちん)
茨城県常陸太田市久米町120-1
TEL:0294-76-0789
URL:https://www.ibaraki-shokusai.net/shop/shops?id=15447

-
そば園 佐竹
そば園 佐竹は、常陸秋そばの自家製粉・挽きぐるみの“田舎そば”が味わえるそば店です。
醤油と味噌を合わせた田舎風のつけけんちんそばは、素朴な味わいに仕上げています。
隣接する「soba&coffee SATAKE」では、「豆乳けんちん」などオリジナリティあふれたそばも提供しています。
茨城県常陸太田市天神林町5-207
TEL:0294-73-2288
URL:https://www.ibaraki-shokusai.net/shop/shops?id=15453
茨城のそばまつり

-
毎年11月から2月にかけて茨城県内各地の産地で、常陸秋そばをはじめとした茨城のそばイベント「茨城のそばまつり」が開催されます。
そば打ち体験

-
茨城県北部は、“最高品質の玄そば”といわれる「常陸秋そば」の産まれ故郷。そんなそばの名産地である県北エリアでは今、そばの魅力を肌で感じられるそば打ち体験を予約制で実施しています。
体験して初めて実感できる驚きと発見がいっぱい!
ぜひ“そば打ち”に挑戦してみてください。
※このページの情報は2023年3月時点のものです。